株式会社糸編 宮浦晋哉さんインタビュー

1987年千葉県生まれ。
杉野服飾大学服飾学部服飾学科モードクリエーションコース卒業後、ロンドンへ留学。
2012年に帰国後、全国の産地を興味のままに周り始める。
2013年 古民家を改修しおでん屋「セコリ荘」オープン。
2017年5月、株式会社糸編に改組し、産地の学校を開校。
キュレーターとして、繊維産地の訪問を重ねながら、各種マッチング、素材製品開発、コンテンツ制作等など幅広く活躍。
公式HP: https://ito-hen.com/
――― 宮浦さんが産地に興味を持たれたきっかけは?
大学卒業後ロンドンに留学してた時に、有名ブランドで働く人達や学校の先生達から、「日本のテキスタイルってすごいよね」とか「クラフトマンシップがいいね」っていう反応が多かったんです。僕はもともとファッションを追いかけてロンドンに行ったつもりだったんですけど、ロンドンで過ごしていた時に、感動したストーリーがテキスタイルに関係することばっかりだったんですね。それから、日本の産地に興味を持つようになって、留学を途中で止めて、帰国して日本の産地を周り始めたんです。
とにかく日本の繊維産地に興味が湧いて、全国のいろんな産地を周りました。当初は仕事というわけではなく、興味の延長です。全国の産地を訪問していく中で、情報をまとめてSNSで発信していたんですけど、それを基に本も自費出版しました。それらがきっかけで、業界の新聞や雑誌から「ページをつくってほしい」「寄稿してほしい」と編集や執筆のオファーをいただくようになって、次第に学生からフリーランサーとしての活動が始まっていきました。
そこから変わらず毎週ずっと産地を周っていたら、徐々にデザイナーさん側からも、「素材のこと詳しいんだったら、企画のお手伝いしてほしい」っていう話が増えていって、商品開発や生地のコーディネートといった仕事が増えてきました。
デザイナーズブランドの社内は数人体制が多いので、僕は外部のデザイナーの壁打ち相手みたいな感じで、いろんな相談を受けてお手伝いをしていました。
――― 築100年の古民家を改修した「セコリ荘」とは?
帰国後すぐに、業界の人達が語り合えるような場所がほしいなと思って、東京の月島にある2階建て古民家を改装して「セコリ荘」というコミュニティスペースを2013年にオープンしたんです。1階の母屋には産地で集めてきたテキスタイルを並べて、ガレージだったスペースではおでん屋さんをはじめました。「おでん」だったら仕込みで料理が完成しているので、営業中の僕も会話に参加して、鍋をつつきながらみんなの輪が広がるいいイメージが湧いたからです。


2階は「雑魚寝ですけど、誰でも泊まれる」と場所を開いていて、しょっちゅうデザイナーさん、編集者さん、バイヤーさん、産地の職人さんが泊まっていってくれました。お風呂がないのでみんなで銭湯に行くところまでセットで。それを丸2年くらいやっていました。当時は、仕事とかお金とか考えてなくて、湧き出る楽しさが原動力でしたが、たくさんの業界内外の方々と繋がることができました。業界の有名な方々ともどんどん出会うことができて、これが準備期間のようになって、活動が本格始動していきました。
その頃に知人の紹介で海外のデザイナーさんからもテキスタイルコーディネートの依頼が来て、やったこともないけど調べながら各国へ輸出業務をしてみたり、その経験も今に活きてます。
最終的には「セコリ荘」の2階をテキスタイルのショールームになって、毎週産地に行って生地が増えていって、1階でおでんと熱燗で盛り上がってテキスタイルの話になると、2階から探してきた生地を囲んで盛り上がる、そんなことを永遠と繰り返していました。

今は、国内外の新しいデザイナーさんからも問い合わせが入ったり、紹介で連絡がきたりっていうのが毎週のようにあって、ヒアリングして産地やマテセンをご紹介したり、各工場をアテンドしたり、ブランドさんにセミナーのようなワークショップに展開することもあります。
――― 宮浦さんに聞けば、全国の産地のことは、何でも相談できるっていうことですね。マテリアルセンターとの違いはどういったところでしょうか?
マテリアルセンターは全国の産地の豊富な生地がひとつの空間に集まる唯一無二の場所です。まだ具体的にどんな企画をするか模索中のデザイナーにとって、1日いるとアイデアが降りてくるような、最高の場所です。すべてのデザイナーにおすすめしたいです。マテセンのDNAじゃないですけど、僕もマテセンの影響を受けていて、東京にもマテセンみたいな場所をつくりたいなぁと夢見ています。東京にいるアパレル関係者は産地を遠くに感じてしまう部分があります。職種や立場によって産地出張できない方も多いので、東京でも産地の魅力をもっと伝えられたらいいなぁと思っています。
最近では、SNSの普及などで、産地からの直接的な発信も増えてきていますし、学生さんたちも、産地に対する興味が増えてきています。これまでマテセンがブレずに発信し・活動し続けてきた種まきが、ようやく実りはじめている感じがします。

――― 宮浦さんが始められた産地の学校について教えて下さい?
2017年、キュレーションという手段で、糸偏産業全体に関わり貢献していきたいという思いから「糸編」という社名にしました。繊維産業・テキスタイルについて体系的に学ぶ場として産地の学校をつくりました。地方の産地には研修プログラムなどがあるんですけど東京では産地やテキスタイルを学べる場所がなかったので。

プログラムは約3ヶ月で1クールで、科目によって毎週専門家の方に来てもらっています。全国の繊維産地の特徴やテキスタイルの知識全般を広く学べる内容となっています。2024年で10期生を終えたところで、延べ600人以上の卒業生がいます。
――― 主にどんな方が学びに来られているのですか?
おおよそ社会人7割、学生3割という割合で、アパレルの企画職や生産管理、就職活動中の服飾学生さんが多いです。異業種から興味があって受講いただく方も多いです。授業を3〜4時間ほど受けてから、さらに教室に数時間残って、「もう教室閉めるよっ」て言うと、そこから居酒屋に移動して終電まで議論するみたいな。そんな熱量を持った受講生が集まってくれています。
――― 服飾学校に通っていて、更に産地の学校でも学ぶって、やる気に満ち溢れていますね!
全国のさまざまな学校に教えに行ってますが、産地に興味を持つ学生さんが確実に増えています。これはマテセン来場の学生が増えているのと一緒ですね。学校だけじゃ足りない学生さんが、産地の学校を活用してくれている状況です。でも新卒で産地就職というのは、事例があまりないので、産地の自治体さんとも連携していい形で繋いでいけたらいいなと思っています。
今、産地の学校の卒業生が全国のいろんな産地に就職しているので、こういった熱い卒業生たちが、産地を盛り上げる火付け役になったり、産地の経営者さんをサポートするとか、そんな活躍を期待しています。
――― いいですね。卒業生の方々が各地で活躍してくれたら本当嬉しいですね!
産地も世代交代が起きていて若い経営者が頑張っていますし、技術を受け継ごうとする若い職人さんも現場に増えてきました。そこに外から産地に飛び込む人も混じって化学反応を起こしていけると理想ですね。僕自身も産地と東京の中間地点で、そんな立場だからこそ機能する形でこの業界の役に立てるように動いていきたいです。

――― マテリアルセンターの存在についてどう思われますか?
マテセンは、産地に興味を持ったときにまず訪れるべき場所です。訪れると、産地の魅力が一瞬で伝わると思います。学校などで「産地は楽しいよ」と言ってもなかなか言葉だけでは刺さらないので、実際に多くの生地に触れてもらうことが一番です。全国各地の産地の特徴がそれぞれ異なることを理解することで、「産地って面白い」という感覚を実感できるはずです。
就職もそうですよね。仕事の楽しさって「実体験」だと思うんですよね。「織機を動かしたらこんな面白いのか」とか「この工場の一員になれたら楽しいかも」みたいな感じ方って、説明会や求人票じゃ伝えられないですよね。これからも繊維産業の楽しさを伝えるために、いろんな産地に学生が訪れて「体験する」という動きもどんどん進めていきたいですね。
――― 宮浦さんの今後の活動について教えて下さい 。
これまでお話させていただいたような活動を地道にやってきた延長が今で、変わらず継続でコツコツやっていけたらいいなと思っています。今年は海外出張が多かったのですが、世界中のデザイナーさんが日本のテキスタイルや産地に興味があることが再確認できました。日本のテキスタイルの輸出につながるような動きを作っていってます。
また業界の未来を考えると、教育が最重要事項で、ファッションやテキスタイルの教育はなかなかアップデートできていません。 学校のカリキュラム作りや、教材作りなどには携わっているのですが。今後も糸偏業界の教育についてはじっくり向き合っていきたいです。
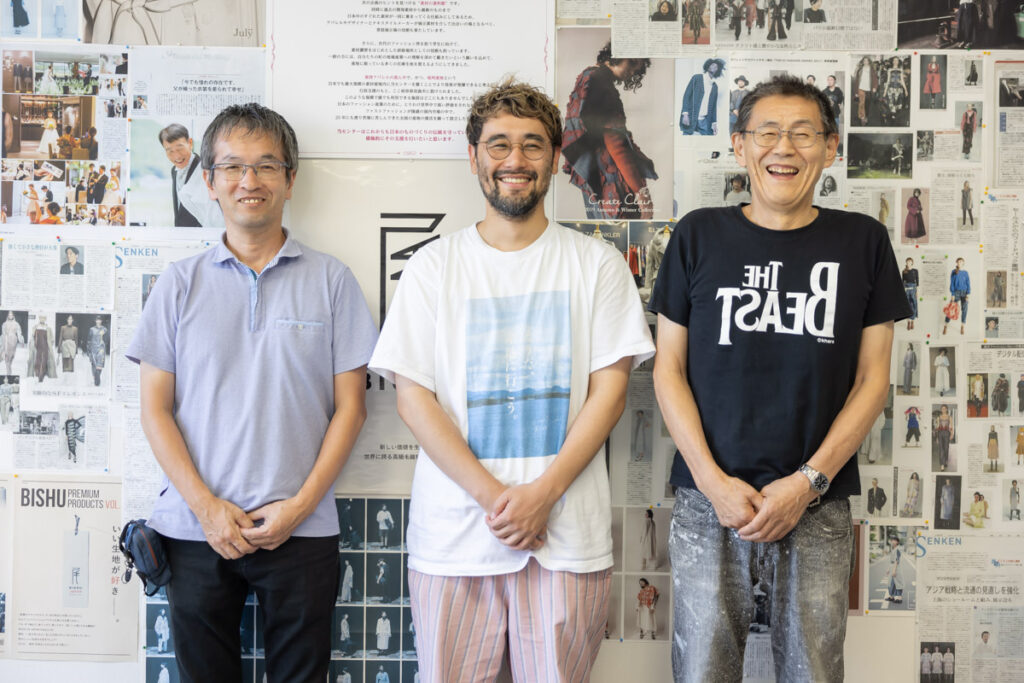
本日は、ご訪問ありがとうございました!そして大変勉強になりました!
今後、宮浦さんのさらなるご活躍を応援しています!
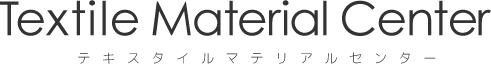 English
English